マイコプラズマ性乳房炎は、酪農および畜産業界にとって長年大きな課題となってきました。日本の酪農の中心地である北海道では、M.bovisなどのマイコプラズマ属菌の感染拡大が頻繁に報告されており、衛生対策や早期発見、感染牛の厳格な管理が求められています。本記事では、牛のマイコプラズマ性乳房炎の発生状況、感染経路、検査・治療方法、現場で求められる対策、今後の課題までをわかりやすくまとめています。

マイコプラズマ性乳房炎の概要と発生の現状
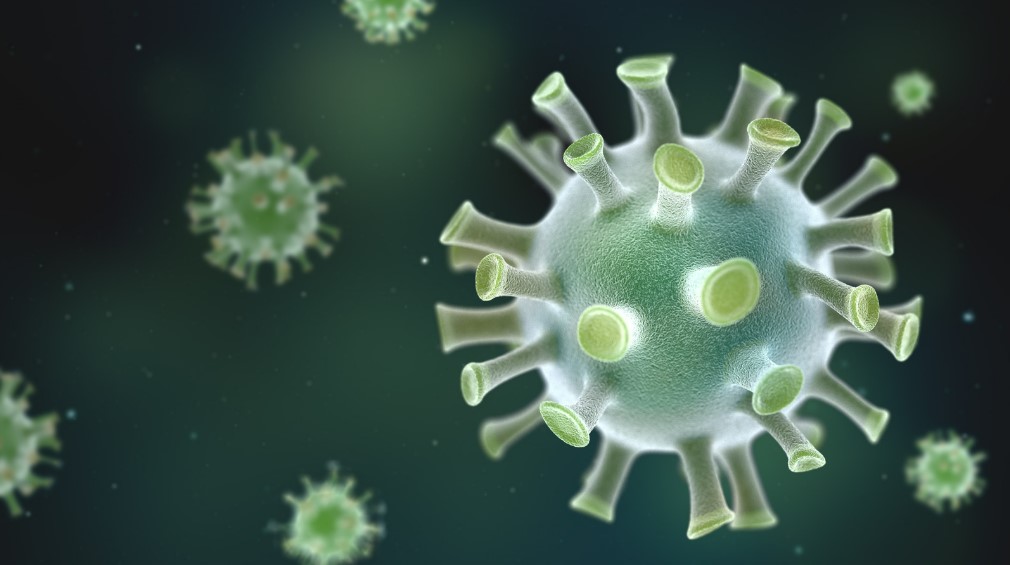
マイコプラズマ性乳房炎の主な原因菌はM.bovis、M.bovigenitalium、M.californicumなどで、これらは牛の乳房炎や肺炎、場合によっては産後感染症など多彩な臨床症状を引き起こします。マイコプラズマ菌は細胞壁を持たず環境抵抗性が低い一方、牛から牛への感染力が強いのが特徴です。
・北海道では2019年~2021年に4農場で流行確認
・乳房感染による乳量減少、生産性低下による経済損失が深刻
・バルク乳検査や農場単位の環境分析実施が拡大
・感染拡大リスク低下のため、早期発見の重要性が高まっている
発生報告が増加していることから、実態把握と感染動向のモニタリングが酪農経営の安定に不可欠です。
検査・診断手法の進歩と課題

臨床症状が現れた場合、乳汁やバルクミルクからのマイコプラズマ菌の検出が診断の基本です。近年は定期的なバルク乳検査、分離培養、PCR法など多様な検査が利用されるようになりました。
・乳汁サンプルの分離培養で主菌種(M.bovisほか)を特定可能
・バルク検査は牛群内の低頻度感染にも有効
・新規導入や初産牛の個別検査により早期発見率向上
・感染初期の菌数低下時は検出漏れのリスクあり
早期の感染拡大防止には、定期検査体制の強化と検査結果の迅速な活用が欠かせません。

治療・淘汰対応の現場実態と選択肢
マイコプラズマ性乳房炎は抗菌薬治療が有効な場合もありますが、M.bovisによる感染などでは薬剤耐性や再発リスクが高く、治療成績は必ずしも安定していません。発症個体の多くは生産性の大幅低下、長期治療の必要性から淘汰や隔離の判断が下されます。
・早期に治療すれば生産復帰例もあるが、経過は個体差が大きい
・5日間程度の抗菌薬治療と乳房モニタリングが基本
・感染牛は搾乳順を最後にし、交差感染を防止
・治療困難例は淘汰・隔離を優先する農場が増加
感染拡大リスクと生産損失を天秤にかけ、農場ごとに最適な管理方針を立てる必要があります。
具体的な感染拡大防止・衛生対策の実践

農場全体での感染予防と拡大抑制のためには、家畜管理ポリシーの策定と教育、定期スクリーニング、イベント時・繁忙期の衛生強化が不可欠です。
・バルク乳スクリーニング検査の定期化で早期摘発
・イベント時・分娩後の管理強化、初産牛の重点検査
・感染疑い牛の即時隔離・淘汰対応
・現場職員への衛生意識啓発と作業手順の教育
・データ分析によるリスク評価と管理の更新
地域行政や畜産法人、酪農協、民間サービス会社の連携による防疫マップ作成や情報共有も拡大しています。

今後の課題と展望
マイコプラズマ性乳房炎対策の成否は、迅速なデータ共有、現場レベルでの実践対策、家畜出荷・導入時の厳格な検査体制整備にかかっています。最新の研究成果や発生マップ、臨床現場の事例を活かし、畜産業界全体での情報連携と防疫意識の底上げが重要です。畜産現場では、乳房炎対策の徹底、現場型のポリシー強化、大規模農場での対応の標準化が急がれます。今後も分離・検査技術や衛生管理の進歩、情報の分析・公開を通じて、牛および農業全体の健康と生産性の維持が求められます。
牛の発熱を検知できる最新ICT機器「CAPSULE SENSE」
今回は「マイコプラズマ性乳房炎」についてご紹介させていただきましたが、乳房炎は早期に発見することで、重症化を防ぐことができる場合があります。
最新のICT機器である「CAPSULE SENSE」は、牛の胃の中で体温を計測できるため、牛の発熱を的確に検知。乳房炎等の発熱を伴う病気の早期発見が可能となります。
只今、お試しキャンペーンも実施しておりますので、ご興味がある方は弊社ホームページからお問い合わせください。
お試しキャンペーン実施中!!
↑お申し込みの方はこちらをクリック↑



