ランピースキン病は、主に牛が罹患するウイルス性の家畜伝染病です。感染した牛の皮膚に結節や潰瘍が現れ、発熱や泌乳量の減少などの症状が見られます。この疾患は畜産業に甚大な影響をもたらすため、国内の各地域や農場では衛生対策と感染拡大防止が急務となっています。感染が確認された場合、ただちに行政や農林水産省へ報告が義務づけられ、強力な防疫措置が講じられます。

ランピースキン病の概要と感染の特徴
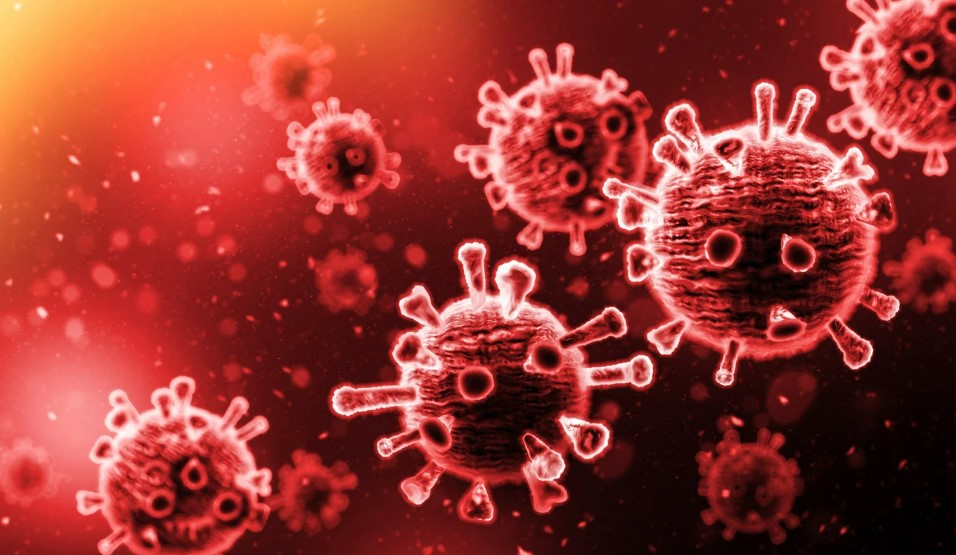
この病気の主な特徴は、ウイルスが牛の皮膚に結節(コブ状のしこり)を形成させる点です。発熱、乳量低下など健康に悪影響を及ぼし、症状が進行すると生産性低下や体重減少につながります。ウイルスは主に吸血性の昆虫(サシバエ、ヌカカ、蚊など)による伝播が指摘されており、農場周辺や施設内の環境衛生、昆虫駆除が感染防止策として重要です。主な症状は下記3つです。
・体表や四肢、頭部に現れる結節や潰瘍
・発熱や元気喪失などの全身症状
・泌乳量の減少、食欲不振や体重減少、などによる生産性の低下
結節は表皮だけでなく、場合によっては口腔や生殖器、内臓にも波及します。症状が重篤になると、牛の健康状態や畜産経営に深刻な打撃を与えるため、早期発見と迅速な対応が求められます。
感染経路と防止のための対策

ランピースキン病の主な感染経路は吸血昆虫の媒介です。ウイルス感染を防ぐには、牛舎内外の消毒や殺虫、飼料や水の衛生管理が不可欠です。農場間や個体間での移動も感染拡大につながるため、農林水産省や自治体では家畜の移動制限を実施し、発症農場や周辺地域への厳格な対策を講じています。
・牛の健康状態をこまめにチェックして早期に異常を見つける
・発症牛や疑似患畜の隔離および殺処分
・農場出入り口、器具、飼料の徹底消毒
・従業員や訪問者に対する衛生教育とマニュアルの配布
・感染が判明した場合は関係機関に速やかに届出・報告
これらの対策を通じて、農場単位での徹底した管理が、感染拡大の防止や早期収束のカギとなります。

国内発生状況と行政対応
2024年11月、福岡県内の乳用牛農場で初めてランピースキン病が国内で確認されました。その後も熊本県を含む複数県で感染が次々と報告され、1か月半という短期間で22農場へと拡大しています。農林水産省は家畜伝染病予防法に基づき、各都道府県と連携しながら疫学調査・監視・殺処分・消毒活動を徹底。さらに、吸血昆虫の発生抑制や防除、農場周辺の環境整備が強化されています。報告や感染経路のトレースは厳しく管理され、感染拡大防止のための様々な施策が実施されています。
ワクチン接種と消毒の現状
現在、発症が確認された地域を中心にランピースキン病ワクチンの接種が農場単位で進められています。これと並行し、消毒によるウイルスの侵入防止策も強化されています。
推奨消毒薬はエタノール、逆性石けん、次亜塩素酸ナトリウムです。
さらに、踏込み消毒槽や器具、飼料保管庫の消毒は頻繁に行い、牛舎とその周囲もこまめに清掃しましょう。サシバエやヌカカが発生しやすい環境の管理にも注意し、昆虫制御剤の活用が推奨されています。
今後の取り組みと持続的対策の必要性

ランピースキン病の発生は、単なる牛1頭の問題にとどまりません。全国の農場にウイルスが広がり、乳量や肉用牛の生産量が減少することで、乳製品や牛肉の流通において、大きな混乱を招く可能性があります。対策は日本国内だけでなく、国際的にも重要な課題となっており、農林水産省や動物衛生研究所などの専門組織は、最新の感染動向や対策マニュアルの更新、情報共有を続けています。感染が疑われる場合や症状が見られる場合は、公式マニュアルや農林水産省の指示に従い、速やかに届出を行うことが必要不可欠です。今後も地域や農場単位で防疫、消毒、ワクチン接種など個別の対策を粘り強く進めることが、日本の畜産業の安全・持続可能性を守る鍵になります。
牛の発熱を検知できる最新ICT機器「CAPSULE SENSE」
今回は「ランピースキン病」についてご紹介させていただきましたが、早期に牛の異常を発見することで、重症化を防ぐことができる場合があります。
最新のICT機器である「CAPSULE SENSE」は、牛の胃の中で体温を計測できるため、牛の発熱を的確に検知。ランピースキン病等の発熱を伴う病気の早期発見が可能となります。
只今、お試しキャンペーンも実施しておりますので、ご興味がある方は弊社ホームページからお問い合わせください。
お試しキャンペーン実施中!!
↑お申し込みの方はこちらをクリック↑



